MIND-EUD Ver.1.1
05.問題分析(問題点と解決策の検討)


Copyright システム企画研修(株)
|
MIND-EUD Ver.1.1
05.問題分析(問題点と解決策の検討) |
 |
 |
Copyright システム企画研修(株) |
||
以上の問題分析を的確に実現する手法として問題点連関図手法があります。
問題点連関図手法は以下の機能を持っています。
問題点連関図のイメージ
| 【左方展開】 | 【右方展開】 | |||
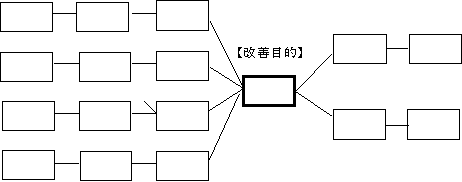 |
||||
|
||||
問題点連関図の利用効果は次のとおりです。
問題点連関図の利用効果
問題点連関図を使って分析を実施すると現実にどのような効果が期待できるのかを、以下の項目立てに従い解説する。
| ◇ | 「やはりそうだ」 | 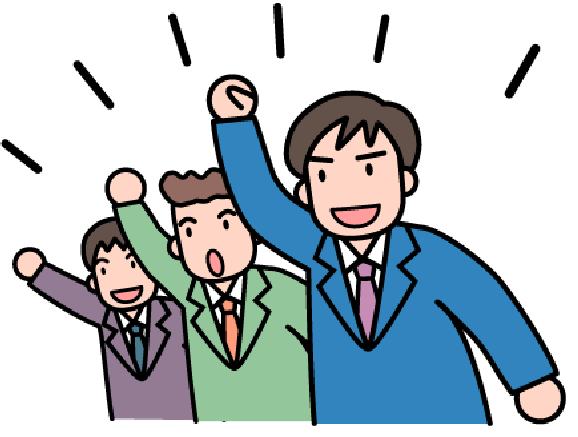 |
||
| ◇ | 「やはりこれをやらねば」 | |||
| ◇ | 「これだけの意義があるのか」 | |||
| ◇ | 「やはりこれしかない」 | |||
| ◇ | 「これは意味ない。あきらめよう」 | |||
| ・ | 漠然と考えていたことが「やはりそうだ」と明確になる。 | |
| ・ | 「やはりこれをやらねば」と実感できる(「ねらい」から)。 | |
| ・ | 「これだけの意義があるのか」と実感できる(同上)。 | |
| ・ | 「やはりこれしかない」と解決策に自信が持てる。 | |
| ・ | 分析しても実施する意義が実感できなかったら、実施しなければならないという思いをあっさり捨てることができる(例:「やせたい」分析をしたが、太っているデメリットが実感できなかったら、「やせねば」という思いは捨てる)。 |
| ◇ | 皆の知恵で新しい知恵が生まれる。 | ||
| ・ | 個人で分析を行う場合は、a.の「確認できる」どまりの場合もある。しかし、複数人で分析を行うと、それぞれが考えていることを引き出して共通の土俵に乗せ、一本化することができる。個人個人から見ると、別の人の考えは、新しい解決策が出てきたように見える。 | |
| ・ | あるいは相互に誘発されて誰も考えていなかった新しい方向が出てくることもある。 |
| ◇ | 原因分解のモデルや5M2Eを用いると、新たな解決策が見つかる。 | ||
| ◇ | 冷静・客観的な分析を実施すると、新たな解決策が見つかる。 | ||
| ・ | 後掲の原因分解のモデル(資料OB−9参照)や5M2E(資料OB−7、OB−8参照)を用いると、あるいは、原理モデルによる原因分解(資料OB−10参照)を行うと、思い込みを脱し、多面的な原因追求が可能で、そこから自分たちが当初意識していなかった解決策に気づくことができる。これらの解決策は必ずしも意外な結果ではない。当然の帰結のような内容である。しかし、当初は想定していなかったのである。 | |
| ・ | 道具立ては手っ取り早くヒントを与えるが、必ずしも道具立てを用いなくても、冷静・客観的に分析を行えば、同じ状況が実現できる。 |
| ◇ | 総花的・総論的・概念的な解決策を避けることができる。 | ||
| ◇ | 偏った解決策を避けることができる。 | ||
| ・ | 目的・ねらいがあいまいなまま分析ないし解決策の検討を行うと、総花的・総論的・概念的な解決策となる危険性がある。 |
| 例: | ・ | 実力主義の人事評価制度を作る。 | 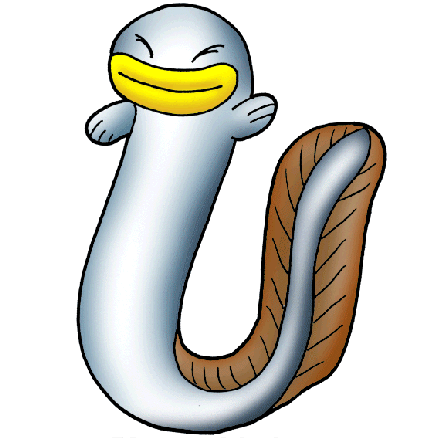 |
||||
| ↓ | |||||||
| あらゆる面で実力が正当に評価される制度を検討する。 | |||||||
| (おそらくこれは暗礁に乗り上げる。) | |||||||
| ・ | 取り扱いアイテム、在庫アイテムの絞り込み | ||||||
| ↓ | |||||||
| 無方針でアイテムを絞ろうとする。 (暗礁に乗りあげるか、大きな悪影響が出る。) |
|||||||
| ↓ | |||||||
| ・ | あるいは、ある特定の対象領域を想定した、偏った解決策となる危険性がある。 |
| 例: | ・ | 受注処理の効率化 | ||
| ↓ | ||||
| 検討する人間が自分の知っている状況を前提に改善策を考えてしまう。 | ||||
| ・ | この点についての詳細な解説は、「4.iv. 右方展開の実施」を参照してください。 |
| ◇ | 解決策の過大評価が避けられる。 | ||
| ◇ | 解決策の強化を引き出すことができる。 | ||
| ◇ | 目的・ねらいの切り下げを決断することができる。 | ||
| ・ | 解決策と目的・ねらいが線でつながっているので、どの解決策がどの問題にどの程度有効で、目的・ねらいにどの程度貢献するかを把握することができる。 | |
| ・ | 同じく、解決策の強化の必要性や目的・ねらいの切り下げの必要性を認識することができる。 | |
| ・ | これは一種の机上シミュレーションで、これを実施しないでいきなり解決策の実現を図ると、「こんなはずではなかった」が起こり得る。 |
問題点連関図手法をさらに詳しくお知りになりたい方は、「問題点連関図手法」をご覧ください。
|
MIND-EUD Ver.1.1
05.問題分析(問題点と解決策の検討) |
 |
 |